【保存版】特定技能1号とは?取得方法・受入れ要件・支援体制まで徹底解説
.jpg)
■特定技能1号とは
人手不足が深刻な日本では、外国人材の受入れが急拡大しています。
令和7年2月時点で293,008人が特定技能1号で就労しており、政府は2024年
から5年間で80万人に受入れを計画しています。
現場作業に従事できる人材として注目され、幅広い業界で進んでいます。
本記事では、特定技能1号の取得ルート、受入れ企業の要件、支援体制などを
網羅的に解説します。
「これから外国人採用を検討したい」企業担当様におすすめです。
■特定技能1号の取得ルート【2種類】
特定技能1号を取得する方法は、以下いずれかです。
▼①技能実習から移行
技能実習2号を良好に修了すると、試験なしで移行可能。
※従事内容が関連している必要あり
▼②試験に合格する
・技能水準試験に合格
・日本語能力(N4相当以上)に合格
■特定技能1号取得までの流れ
▼A)日本国内に在住している場合(例:技能実習修了)
1,試験合格/技能実習
2,雇用契約を締結
3,企業が支援計画を策定(事前ガイダンス)
4,入管へ申請→許可
5,就労開始・生活オリエンテーション
▼B)海外からの招聘の場合
1,試験合格
2,雇用契約を締結
3,支援計画策定
4,在留資格認定証明書→交付
5,現地日本大使館で査証(VISA)発給
6,入国→就労開始
■【基準①】特定技能外国人本人の要件
▼共有要件(1号/2号)
・18歳以上
・健康状態が良好
・有効な旅券を所持
・保証金の徴収を受けていない
・費用支払いの内容を把握している
・送出国手続きを適正に行っている
・居住費等が適正で、費用明細が提示されている
・各分野で定める基準に適合
▼特定技能1号のみ
・必要技能・日本語を試験等で証明
※技能実習2号の良好修了者は免除
・通算在留期間が5年以内
▼特定技能2号のみ
・必要技能を試験等で証明
・技能実習経験者は本国への技能移転に務めること
■【基準②】受入れ企業(特定技能所属機関)の要件
▼雇用契約について
・分野で定める業務に従事させる
・所定労働時間が通常労働者と同等
・報酬が日本人と同等以上
・差別待遇の禁止
・一時帰国に配慮
・派遣の場合は派遣期間・派遣先を明示
・帰国旅費負担
・生活/健康状況の把握
・分野基準への適合
▼受入れ機関の適格性
・労働・社会保険・税法を遵守
・1年以内に非自発的離職者を出していない
・行方不明者を発生させていない
・欠格事由なし(出入国/労働違反など)
・活動内容書面の保管(1年以上)
・保証金・違約金契約を締結していない
・支援費用を外国人へ負担させない
・労災保険を届出済
・体制が適切に整備
・給与は口座振込
・地方自治体の共生協力に協力
・分野基準への適合
■【基準③】支援計画(企業or登録支援機関)
外国人を受け入れる企業は10項目の支援を実施する必要があります。
▼支援内容(10項目)
1,事前ガイダンス
2,出入国送迎
3,住居確保・生活に必要な手続き支援
4,生活オリエンテーション
5,公的手続きの同行
6,日本語学習の機会提供
7,相談・苦情対応
8,日本人との交流促進
9,転職支援(企業都合退職の場合)
10,定期面談・行政通知
※自社で実施できない場合は、登録支援機関へ委託可能
■まとめ|特定技能1号で受入れで重要なポイント
| 項目 | キーワード |
|---|---|
| 取得ルート | 技能実習→移行/試験合格 |
| 在留期間 | 通算5年 |
| 企業要件 | 法令順守・同等報酬・支援体制 |
| 支援計画 | 10項目の義務 |
| 委託支援 | 登録支援機関へ委託可 |
特定技能1号は、
即戦力となる外国人材を受け入れたい企業にとって有効な制度です。
受入れには
・法令順守
・支援体制
・適正な雇用管理
が必須です。
■外国人材採用・特定技能手続きは専門家へ
・手続きが難しい
・何から始めればいいかわからない
・支援を自社でできない
こうした課題は専門家に相談することでスムーズに採用できます。
要件の確認や書類作成などで不安がある方は、下記の無料相談にお気軽にご相談ください。
岐阜市の帰化申請ステーション
LINE相談はこちら▼

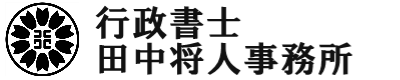


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)